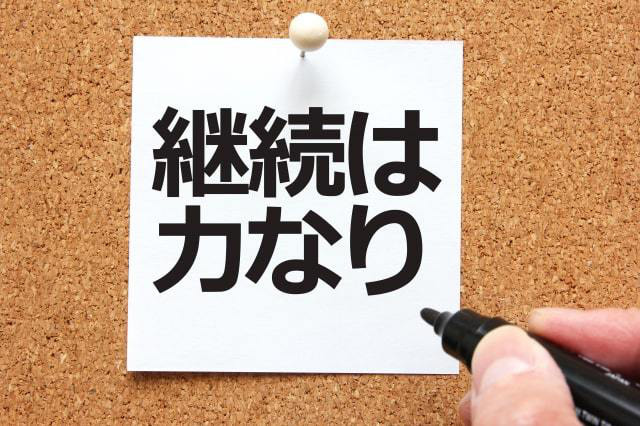インタビュー 2017.04.28
ライフネット生命インタビュー(3)
保険会社にとって、保険商品の一つひとつは、まさに自社の「顔」ともいえます。ロゴ、WEB、すべてにおいて「わかりやすさ」を大切にしているライフネット生命。その理念に基づく思いは、商品にどう反映されているのでしょうか?また、ライフネット生命ならではの商品開発プロセスとは?インタビュー最終回は、経営戦略本部商品開発部長の高橋賢司さんにお話しを伺いました。
第3回「商品開発」編
商品開発は「人々の思いを反映すること」

商品開発者とは「お客さまの思い」「会社・社員の思い」を繋ぐ人
1つの商品ができるまでには、社員の思い、お客さまの要望など、多くの人の気持ちが行きかうと想像します。商品開発部の高橋さんは、そんな思いを商品に反映させるという大切な役割を担っていらっしゃるのです。
高橋さんは、保険業界一筋、長く商品開発畑を歩んでこられました。異業種出身者が多いといわれるライフネット生命の中においては、業界の歴史を知る貴重な存在です。まず、実際にはどんなお仕事をされているのかを伺ってみました。

「実は、商品開発は新商品を生み出すだけでなく、いまある商品をさらに進化させるという作業が多いのです。お客さまの声、現場で販売している人の声を反映したり、他社の商品のいいところを研究したりなど、あらゆるものを取り入れることを常に考えています。ライフネット生命に来て、最初に取り組んだ就業不能保険『働く人への保険2』もそうでした」
『働く人への保険』は、ライフネット生命が、生命保険会社としては初めて、個人向けに発売した長期型の就業不能保険です。出口会長や岩瀬社長がライフネット生命を立ち上げる前からあたためていた、想い入れのある商品と聞きます。一家の大黒柱の死亡保障だけでなく、働く生活者一人ひとりが働けなくなったときの備えが欠かせない、約3割の人が就業不能保険に加入すると言われているアメリカに対し、普及が遅れている日本の現状をなんとかしたいという、お二人の強い気持ちから生み出されたものです。
そして、発売から6年、高橋さんたち開発チームによって、より良いものへと改定されたのが『働く人への保険2』です。改定にあたってこだわったことは「お客さまのニーズにあった選択肢を用意すること」。実際の保障内容を見てみると、従来のものに比べ、保険期間、給付金の受け取り方法などの選択肢が増えています。多くの人たちの声が反映された結果だと知ると、改定された理由がわかり、保障内容の一つひとつが身近に思えてきます。商品に込められた物語や舞台裏を知ることは、商品をより深く理解することにも繋がると感じました。

他部署と連携した開発プロセスがライフネット生命の強み
一方で、新しい商品の開発は、どんなプロセスで取り組まれているのでしょうか。
「新しい商品を作るときは、どんなターゲット層に向けて保険を作るかが最初のデザインです。そして、既存の商品との関係性も考えながら保険の種類を決めていきます。まずプロトタイプを作り、グループインタビューやWEB調査などを通して少しずつ変更して作り上げていきます。」
開発段階でもWEB調査を活用するとは、さすがWEB販売のパイオニア、ライフネット生命さんですね。一方、苦労について伺うと、こんな答えが返ってきました。
「当社の商品開発部は少人数。ですから、商品開発には会社全体でプロジェクトを組みます。あらかじめ事務担当の声も聴いて、事務フローも考えておくなど、他部署からも1~2人ずつ集まって、2~30人体制で取り組みます。」
こういった全社あげての連携体制こそ、大手の保険会社にはない最大の武器かもしれません。早い段階から、事務やWEBチームといった他部署の人たちの意見を取り入れることで、お客さまが保険を選ぶ時には「よりわかりやすく」、申し込みをする時・保険金が支払われる時には「より使いやすい」商品に繋がるのでしょう。
「社全体の『顔』がみえる範囲で取り組めるので、社員同士の連携もスムーズですし、決断のスピードも上がります。」そうおっしゃる高橋さん。ふと「顔が見えること」を大切にデザインされた、あのロゴマークが目に浮かびます。社員同士の顔が近いことも、商品開発のうえで強みとなっているようです。
商品を増やしても「わかりやすさ」は大切にしたい
ライフネット生命の商品ラインナップについても伺ってみました。ライフネット生命の大きな特徴の1つは、商品数が少ないこと。大きくは、死亡定期保険、終身医療保険、就業不能保険の3種です。わかりやすさのために、あえて商品の数を少なくしているのでしょうか?

「商品を少なくしておくことが、必ずしもシンプルとは思っていません。保障が足りていない部分があれば、商品を増やすことも考えています。ただし、商品を増やしても、もちろんわかりやすさは捨てません。そのために、メッセージを乗せたり、組み合わせを考えたりの工夫は必要でしょうね。」
保障を必要とする人がいる限り、そのニーズを満たす商品を作っていきたいと意気込む高橋さん。日頃から、世の中の保障ニーズにアンテナを巡らせているといいます。また、他部署の社員からも、新商品のアイデアを募ることも多いとか。開発者だけでなく、多くの社員のアイデアが、お客さまの暮しを守ることに繋がるって、なんだか素敵です。
「商品開発のピッチを上げて行ける体制づくりが現在の目標です。商品を世に出す時が一番の喜び」だそうです。今後もユニークで役立つ商品が登場しそうな予感。期待も膨らみます!
「わかりやすさ」と「思い」が伝わる商品は強い
保険というのは、いざという時、わたしたちの隣に寄り添ってくれる味方です。とはいうものの、一般的に保険のパンフレットは商品のしくみや保険料、注意点などが多く、商品そのものに温もりを感じることはあまりありません。パンフレットの記載ルールなどがとても厳しいため、仕方のないことではありますが、商品を作った人の顔や、「その商品に込められた思い」を知れば、保険も「難しい」ではなく、「いいな」「ありがたいな」に変わると思うのです。

デザインというと、ビジュアル的なものばかりがイメージされがちですが、いろいろな要素をどうバランスよく組み合わせるか、そしてそれがどう人の役に立つのかもデザインです。保険商品も、お客さまに安心していただき、いざという時には役立つようにデザインされたものと考えられます。
ライフネット生命さんの商品設計は、その過程で、社内や社外から集めた多くの声が、役立つためのデザイン精度をぐっと上げているように思いました。商品デザイン、ブランドイメージ、視覚を重視した伝え方、トータルでデザインできているのがなにより素敵です!
私たちが普段使う金融商品は、使い勝手やネーミング、中身の伝え方、お客さまのフォローに至るまで、どこをとっても「わかりやすく、使いやすい」ことが重要だと、わたしたち金融デザインチームは考えています。
「正直に、わかりやすく、安くて、便利に」をマニフェストとするライフネット生命。「難しい金融商品を普通に伝えたい」そう取り組むわれわれ金融デザインチームの想いとも重なったインタビュー。心から応援したい会社の1つになりました。


EMIKO TAKAGI
ライター
温暖な知多半島が生んだ、遅咲きの天然系ファイナンシャルプランナー。元銀行員、カラリスト、手書きPOPライター。地元愛がこのうえなく、地域に暮らす人々のマネー相談に「ハイ、よろこんで~!」と奮闘中。そのかたわら「書きもの」という手段で、お金の情報を発信する魅力にもとりつかれ、わかりやすさを追求した記事執筆にも取り組む日々。自分の最大の武器は「普通の人の普通の感覚」を持ち続けていること。街のオーケストラのフルート吹きでもあり、チームでなにかを創りあげる力も備えていると自負している。趣味は、ミュージカル・歌舞伎をはじめとした舞台鑑賞。趣味にお金を投じ過ぎるも、「心が豊かになるものにはお金を使おう」がお金に対するスタンス。また、新聞スクラップが趣味の新聞マニアでもある。「金融を普通に」部員として情報感度を磨く日々を過ごしている。>>プロフィール